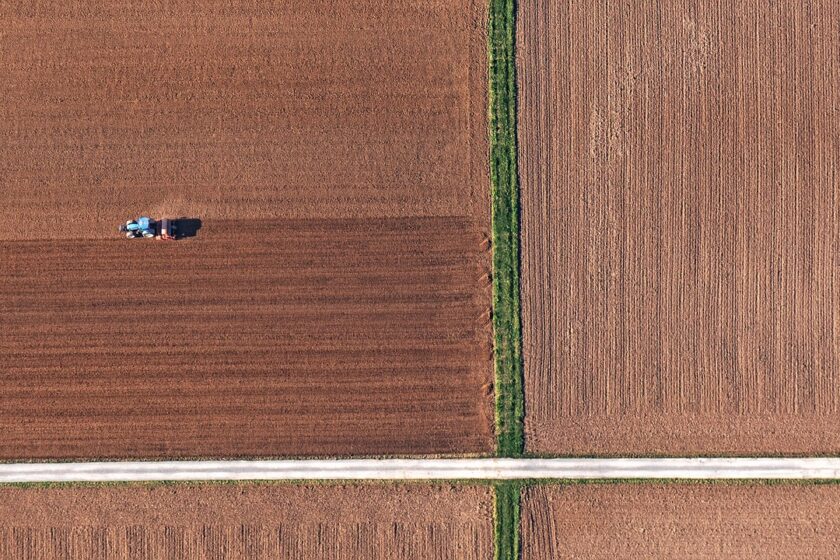この記事では、「社会的インパクト評価」とは何で、どのような目的のために行うのかや、プログラム評価との関係、評価の5原則、評価の実施方法について解説します。
<目次>
社会的インパクト評価の意味と目的
社会的インパクト評価とは何か
「社会的インパクト」と、それを評価する「社会的インパクト評価」について、内閣府のガイドラインでは、以下のように定義されています1。
社会的インパクト:
短期、長期の変化を含め、当該事業や活動の結果として生じた社会的、環境的なアウトカム
社会的インパクト評価:
社会的インパクトを定量的・定性的に把握し、当該事業や活動について価値判断を加えること
ただし、その定義や理解には多くのバリエーションが存在し、広く標準化された評価手法はまだ確立されていません。国際的に合意された基準が現時点では存在しないという点で、未だ発展途上にある概念と捉える必要があります。
また上記ガイドラインでは、社会的インパクト評価について「事業や活動についての『価値判断』を行うための評価プロセス全体(①計画、②実行、③分析、④報告・活用)を指すもの」とも表現されており、インパクトの評価だけでなく、評価を通じた事業全体のマネジメントの手段として位置づけられています。
社会的インパクト評価は、もともと環境アセスメントに端を発しており、特に社会的投資の領域におけるニーズへの対応として考案された手法であるという点で、民間投資の流れと強い結びつきがあります2。社会的価値を貨幣換算することで費用便益分析を行う「SROI(Social Return on Investment)」は、社会的インパクト評価の一類型であり、アウトカムの貨幣価値換算による評価に主眼を置いている点が特徴です。
なお、「社会的インパクト評価」は、これと類似する「インパクト評価」とは異なる点には注意が必要です。「社会的インパクト評価」は厳密な因果関係の評価を必要としないことが一般的であるのに対し、「インパクト評価」は学術的な評価学・評価研究における概念であり、事業とその成果の帰属性を考慮し、因果関係について厳密な評価を行う点が重要な違いです。
社会的インパクト評価を実施する目的
「社会的インパクト評価」は、民間の投資家や金融機関による社会的事業への投資が増える中で、投資先事業が生み出す社会的価値を客観的な指標で評価し、投資を通じた社会的価値の創出を最大化する、というニーズに応える一つの手段として導入が拡がったものです。
休眠預金を活用して民間公益活動の促進を図る「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(2023)3では、事業による成果について「社会的インパクト評価」を実施し、成果の可視化に取り組むことが義務付けられています。ここでは、評価の目的として、
- 資金の活用の成果を積極的に情報発信することで、広く国民の理解を得る
- 評価結果を資源配分に反映し、民間公益活動を効果的・効率的に行う
- 厳正な評価による活動の質向上、独創的・革新的な活動の発掘、民間資金・人材の獲得
の3つが挙げられていますが、これらはそれぞれ「アカウンタビリティ」「資源の適正配分」「活動の改善・刷新」に当たります。評価自体を目的とするのではなく、評価を通じて、社会課題の解決に向けた取り組み全体を改善・強化していくという考え方が強調されています。
また、UNDP等によって設立されたIMP(Impact Management Project)のガイドラインにおいては、「社会的インパクト・マネジメント」という概念が示されました。これは、組織や事業のマネジメントプロセスの中に社会的インパクトを位置づけ、その評価を通じて事業や投資を通じた社会的価値の創出を継続的に向上させていくことを意味します。
プログラム評価との関係性
社会課題の解決に向けた取り組み全体を「プログラム」と捉え、体系的な評価を通じて、その取り組みの価値の判断や、質の改善につながる情報を得る活動を、「プログラム評価(Program Evaluation)」と呼びます。
プログラム評価では、一般的に「評価」としてイメージされる、「取り組みによる成果の評価」(アウトカム・インパクト評価)だけでなく、ニーズ評価・セオリー評価・プロセス評価・効率性評価といった異なる目的の評価を組み合わせることで、取り組み全体の包括的な評価を行うことが特徴です。米国においては、1960年代に政策評価のためのツールとして導入され4、今日に至るまで主要な政策評価手法の一つとして位置付けられています。
社会的インパクト評価においても、プログラム評価の要素を取り入れ、純粋な成果(インパクト)の評価だけでなく、取組み全体の体系的な評価を行うことで価値の判断につなげる、という考え方が一般的になりつつあります。
また、社会的インパクトが「短期、長期の変化を含め、当該事業や活動の成果として生じた社会的、環境的なアウトカム」と定義されることから、その評価を行う「社会的インパクト評価」は、中長期的なアウトカムに対する成果の測定を行うプログラム評価の一形態として理解することができます5。
プログラム評価の詳細についてはこちらのページをご覧ください。
社会的インパクト評価の実施方法
以下では、内閣府によるガイドライン1や、GSG Impact JAPAN(旧:GSG国内諮問委員会)による実践マニュアル6などにおいて示された内容をもとに、社会的インパクト評価の実施方法について要点を整理します。
社会的インパクト評価の原則
社会的インパクト評価を実施する際の前提として、「社会的インパクト評価の原則」という5つの項目の重要性が指摘されています1。評価の目的やニーズに応じて評価方法の多様性を確保しながらも、評価に対する信頼性や比較可能性を維持するために一定のルールに則り評価を実施することが必要、との考えから定められたものです。
実際の評価にあたっては、これらの原則を常に念頭に置きながら、評価を計画し実施していくことが必要です。
| 重要性 (マテリアリティ) |
経営者や従業員、資金仲介者、資金提供者を中心とした利害関係者が事業・活動を理解するための情報や、資金提供の意思決定を左右する社会的インパクトに関する情報が含まれるべき。 |
| ② 比例性 | 評価の目的、評価を実施する組織の規模、組織が利用可能な資源に応じて評価の方法や、報告・情報開示の方法は選択されるべき。 |
| ③ 比較可能性 | 比較が可能となるよう、以前のレポートと同じ期間、同じ対象と活動、同じ評価方法で関連づけられ、同じ構造をもって報告されるべき。 |
| ④ 利害関係者の参加・協働 | 社会的インパクト評価に当たっては、利害関係者が幅広く参加・協働すべき。 |
| ⑤ 透明性 | 分析が正確かつ誠実になされた根拠を提示・報告し、利害関係者とその根拠について議論できるようにすべき。 |
①評価の目的・対象・進め方の決定
社会的インパクト評価のあり方は一様ではありません。事業やプログラムがどのような変化を受益者や社会に生み出しているかを定量的・定性的に評価することが社会的インパクト評価ですが、その活用方法は多岐にわたります。
事業者として、評価からなにを学び、どのように事業改善へとつなげたいのか、誰に対してどのように説明責任を果たしたいのかによって、評価の内容や進め方、レポーティングの仕方は異なります。これらについて、まず関係者の間でよく話し合い、共通理解を得ることが最初のステップとなります。
この際、評価の対象となる社会的価値は本来的には主観的な価値の集合体であり、客観的な評価が難しいものであるという認識に立ち、「利害関係者の参加・協働」「透明性」の原則に基づいて、多様なステークホルダーの評価への参加などを通じた、妥当性・透明性の高い評価の実施を目指すことが重要です。
また、どのようなステークホルダーに、どのような形で評価に参加してもらうことが、評価目的の達成に資するものとなるのか、「重要性」や「比例性」の原則も念頭に置きながら、評価の対象とする事業や受益者、評価の進め方などについて判断します。
②ロジックモデルの作成
評価の目的や対象、進め方について合意が得られたら、次にロジックモデルを作成します。ロジックモデルは、事業やプログラムなどの取り組みが目指す成果・目的と、その達成のために用いられる手段との関係を、体系的かつ論理的に表現したモデルのことを指します。社会的インパクト評価を行う事業の設計図にあたります。
ロジックモデルを作成することにより、事業が最終的に目指す成果が、「どのような活動の結果として・なぜ実現されるのか、その活動を行うために必要な資源はどのようなものか」、という論理構造が可視化されます。これによって、事業に携わる人々が共通の認識を持つことができるとともに、事業の支援者に対しても、事業の価値や妥当性を明確に示すことが可能となります。
ロジックモデルの基本要素は以下の4つから構成されます。
- 投入(インプット) :事業に対して投入される人・モノ・カネ・情報などの資源
- 活動(アクティビティ):インプットを使い行われる実際の活動
- 産出(アウトプット) :活動の結果として生み出される財・サービスなど
- 成果(アウトカム) :事業の実施後における社会の状態の変化
また、「成果(アウトカム)」は、成果が実現される時間軸やその効果の波及プロセスによって、
- 事業による直接的な成果を表す「直接アウトカム」
- 最終アウトカムの実現に貢献する成果を表す「中間アウトカム」
- 最終的に実現を目指す社会の状態を表す「最終アウトカム」
の3つに分けられ、特に「最終アウトカム」は「インパクト」とも呼ばれます。
以下は、最も基本的なロジックモデルの構成の一例です。インプットから最終成果に至るまでの論理構造が、一つの流れとして表現されることが、ロジックモデルの大きな特徴です。
作成:Intelligence In Society
ロジックモデルの詳細についてはこちらのページをご覧ください。
③アウトカムの設定と測定方法の決定
ロジックモデルが作成できたら、記載されたアウトカムのうち、どのアウトカムを評価対象とするかを整理します。これは評価の目的に基づいて、「評価の範囲」を決めることに当たります。
社会課題の解決に向けた活動は、短期的・長期的に様々な影響を生じさせますが、その全てを把握することは困難です。ロジックモデルに記載されたアウトカムのうち、「どのアウトカムの、どの受益者について、どこまでの時間軸で」評価の対象とするのかを明確にし、アウトカムに優先順位を付けることで実際の評価対象とするアウトカムを決定します。
次に、対象のアウトカムを「どのような指標について、どのような測定方法で」評価するかを整理します。アウトカムを測定する指標と測定方法は、定量・定性含め多様な方法が存在し、測定方法によって得られる情報の厳密性も様々です。
インパクトの厳密な測定には一定の専門知識や費用・工数が必要であり、すべての事業の評価において厳密な評価を求めることは現実的ではありません。重要なのは、上記の「重要性」「比例性」の原則などに基づいて最適な手法を選択し、事業に携わる人々が納得できる形で評価を行うことです。
また、関係者が納得できる評価を実施する上で必要な知識やスキルが組織内にあり、自分たちで評価を実施できるのか、あるいは外部の専門家の支援を求める必要があるのか、についてもこのタイミングで判断を行うことになります。
④データの収集および分析
評価対象となるアウトカムとその指標が決まったら、実際のデータの収集に入ります。この際、アウトカムの評価において事業の実施前・実施後の比較データを必要とする場合には、事業開始前にもデータを収集しておく必要があることに注意が必要です。
また、実際のデータの収集においては、データに基づく評価結果ができる限り高い妥当性を持つよう配慮することが重要です。これには、データ収集の対象者の選定(サンプリング)、データ収集の方法、データ収集のタイミングなどが含まれます。
事業の受益者全員からサーベイ(アンケート)などによってデータを収集することは現実的ではない場合が多く、実際のデータ収集においては受益者全体から一部の対象者を選別することになります。この際、事業の効果に影響を与えうる要素(例えば、年齢・所得・学歴などの属性)が、受益者全体とデータ収集の対象者で十分に類似していなければ、その対象者から得られたデータは事業の効果について誤った情報を提供する可能性があります。
また、データ収集の方法が、対象者によってWEBサーベイ・紙によるサーベイなどと異なっていたり、事業実施からデータ収集までの期間が対象者によって大きく異なっている場合などは、それらの違いがデータに影響を与え、評価に無用な歪みを生じさせる可能性があります。
事業と成果の間の帰属性をより高い精度で評価する場合には、因果関係を適切に評価するために一定の専門的知識が必要となります。例えば、評価結果に影響を与える要素の一つに、事業を実施しなかったとしても発生していたインパクトを表す「デッド・ウェイト(死荷重)」がありますが、これに対する対処は「因果推論」などの手法を適用することで可能となります。
評価においては、必要に応じて、外部の専門家による支援を求めることも選択肢の一つとなります。
統計的因果推論についての詳細は、こちらのページをご覧ください。
⑤報告・事業改善
データの収集と成果の測定が完了すると、それをレポートとしてまとめる作業に入ります。評価を行う目的は、支援者への成果報告(アカウンタビリティ)、さらなる事業資金の獲得に向けたPR 、事業の改善・刷新、経営資源の配分に関する意思決定など様々ですが、重要なのは評価レポートがこれらの目的のために有効に活用されることです。
そのためには、必要以上の詳細や形式的要素を盛り込んだ重厚なレポートではなく、主たるレポートの読み手にとって、必要とする情報が過不足なく記載されたものである必要があります。
レポートのアウトラインとしては、例えば以下の基本的な質問事項に答える構成が考えられます6。
| 1. 事業目標 | どのような社会課題の解決を目指したのですか |
| 2. ロジックモデル | その問題に対してどう取り組み、どのようなステップを踏むことで問題解決に貢献できると考えたのですか |
| 3. 活動内容 | 具体的に何を行ったのですか |
| 4. 成果・アウトカム | その結果何を成し遂げましたか |
| 5. 指標に照らし合わせたデータ分析 | アウトカムを達成したと言える根拠は何ですか |
| 6. 振り返りポイント | 評価からの学び、今後の改善のための教訓はなんですか |
また、社会的インパクト評価の目的として、アカウンタビリティと並んで重要なのは、評価を通じた事業の継続的な改善・刷新です。
例えば、事業のアウトカムに対する評価結果が目標に対して不十分なものであった場合、
などを包括的に検討することで、事業の改善に必要なポイントを明らかにすることができます。
また、仮にアウトカムの評価結果が目標をクリアするものであった場合でも、
などを検討することは、今後の事業運営や新たな事業開発の在り方を検討する上で、貴重な情報を提供します。
また、上記の点を検討する中で、アウトカム指標の設定やその測定に採用した手法、収集されたデータの質や量について、不十分だった点などが見えてくることがあります。ここで明らかになった課題を、今後の評価における目的設定・手法検討・データ収集などの改善につなげることで、社会的インパクト評価自体の質の向上を図っていくことも重要です。
ここまで、社会的インパクト評価について、その意味や目的、実施方法について解説しました。社会的インパクト評価の実施には、関連するトピックであるプログラム評価やロジックモデル、因果推論などに関して一定の前提知識を持っていることが必要です。
社会的インパクト評価に関する全ての記事は、以下のページからご覧いただけます。
その他、当記事に関連するトピックの詳細については、以下のページをご覧ください。
参考文献・注記:
1. 内閣府, 社会的インパクト評価検討ワーキング・グループ (2016)「社会的インパクト評価の推進に向けて」
2. 源由理子・大島巌(2020)『プログラム評価ハンドブック-社会課題解決に向けた評価方法の基礎・応用-』, 晃洋書房
3. 内閣府 (2023)「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」
4. 田辺智子(2014)「業績測定を補完するプログラム評価の役割-米国のGPRAMAの事例をもとに-」『日本評価究』, 14(2): 1-16
5. 伊藤健・玉村雅敏・植野準太(2021)「プログラム評価の一類型としての「社会的インパクト評価」の課題と可能性」『日本評価究』, 21(2): 89-101
6. GSG Impact JAPAN, 社会的インパクト評価ワーキング・グループ (2017)「社会的インパクト評価ツールセット実践マニュアル」